世の中には沢山の資格がある。1番効力があるのが「国家資格」で、これがないとその業務を行いない場合もある。
当然、士業(しぎょう)と呼ばれる資格は国家資格に該当する。
弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士・弁理士・土地家屋調査士・海事代理士。
あなたはどれを受験?超難関資格の士業に合格して人生を逆転させる。

「公的資格」は必須でないが、あると社会的に効力がある。ファイナンシャルプランナーや販売士検定が公的資格だ。
それ以外の資格は民間団体が試験を行っていて、効力が低い。合格しても社会的に認められず、自己満足で終わる事が多い。
自己満足と言っても年金や税金の知識は手に入る。節約生活をしたいなら大いに役立つ。
ファイナンシャルプランナーは仕事より、自分の生活で使える資格。

FPの仕事1マネーセミナーの開催「お金の貯め方と使い方を学ぶ無料マネーセミナー5選!独身女性限定」

FPの仕事2ライフプラン作成「生命保険の窓口はどこがいい?ライフプラン見直し無料相談5選!」

究極の資格は司法試験(弁護士)

最高難度の司法試験は10年かけて合格する人もいる程。
近年の合格率は23%前後だが、頭脳派エリート集団が受験しての合格率だから並大抵の勉強では合格できない。
司法試験合格後は司法修習生として研修を受ける。無事終えれば法曹(裁判官・検察官・弁護士)になれる。
その裁判所・検察庁・法務局への提出書類を作成するのが司法書士。その他、土地建物の登記や会社の登記(法人登記)の仕事がある。
合格率は3%前後で、合格したら新人研修を受けるのが一般的。先輩の司法書士事務所で働いて業務を覚えるのは他の士業と同様。



公認会計士は受験資格がないから誰でも受験できる。

公認会計士の合格率は8%前後で推移している。20代の若い世代が受験する傾向にある。
試験に合格後、実務経験が2年あれば公認会計士になれる。公認会計士の試験前に簿記1級を取得するのも珍しくない。
公認会計士は受験資格がないので、誰でも受験できる。公認会計士や税理士試験合格に10年かける受験生もいる。
税理士の受験資格は簿記1級。

税理士は受験資格が必要で、短期大学や専門学校の卒業が必要。
特定試験合格でも受験できて、日商簿記1級を取得して税理士を目指す人もいる。
公認会計士と違って税理士は科目合格制度がある。その為、1年に1科目合格すれば5年で税理士になれる。
だが、各科目の合格率は10%と低いので、甘くない。



近年、超難関資格となった社会保険労務士。

これまで8%前後で推移してきた合格率は近年4%前後となっている。
受験資格は税理士同様、短期大学や専門学校の卒業で、行政書士資格があれば受験できる。
社会保険労務士は特殊な試験で、合格基準がない。
社労士試験終了後の採点によって、合格基準(合格率)が決められる。
試験で高得点を上げた受験生が多ければ、合格基準も引き上げられる。合格者数・合格率が調整されるのだ。
社会保険労務士試験。実務未経験だと試験に合格しても稼げない?

毎年選択式や択一式の合格基準が変動するのはその為だ。
競争の試験だから受験生が多いほど、勝ち上がるのは難しい。
合格率8.5%だった2006年(6万人受験)より合格率8.6%の2010年(7万人受験)の方が合格するのが難しいとも言える。
同じ合格率なら7万人倒すより6万人倒す方が楽だ。

社労士に合格するならこちら「社会保険労務士の試験対策!オンラインの通信教育講座で合格する」

社労士の受験勉強から開業まではこちら「社会保険労務士試験に合格して転職採用!開業登録と年会費はいくら?」

弁理士・行政書士・中小企業診断士。

弁理士は特許庁への申請手続き専門家。弁理士も行政書士も合格率は10%程度。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士資格があれば行政書士の仕事も行える。
行政書士は法律資格の登竜門でもある。中小企業診断士は名称独占資格であり、資格がなくてもその仕事は行える。
上記のように弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士・弁理士・土地家屋調査士の士業はどれも超高難度の試験だ。
時には人間の生活を捨てて勉強する必要がある。純粋にどの仕事がしたいのかを自問自答して受験しよう。
社労士試験合格後の仕事探しはMS-Japanとリクルートエージェント
がお勧め!

就転職方法は「社会保険労務士の求人探し5選!未経験者が正社員で就職する方法」を読もう!


受験生なら読むべき弁護士・税理士・公認会計士の成功物語。
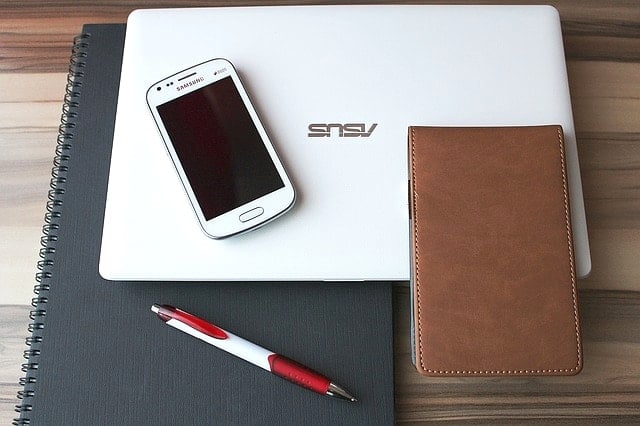
日本には「士業」と言って資格(登録)がなければその仕事を行ってはいけない業務(業務独占)がある。
名を上げると弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士だ。
それら業務独占に対して資格がなくても仕事ができるのが、名称独占と言われる。
中小企業診断士やファイナンシャルプランナー(技能士・AFP)だ。
名称独占は資格がなくてもその仕事は行える。
だが、資格が無いのに中小企業診断士やファイナンシャルプランナー(技能士・AFP)を名乗れない事となる。
日本には膨大な数の「資格」があるが、資格取得だけでは成功するのは難しい。やはり、実務経験や人脈が必要なのだ。

FPについてはこちら「ファイナンシャルプランナー2級3級試験のeラーニングスクール5選!」

司法(弁護士)試験に13回挑戦した主婦。

受験資格や試験制度は変更される事がある。なので、本が出版された時点での内容をそのまま記載する。
最初に紹介するのは「他の誰でもない私を探して(スチュワーデス弁護士になる)」
今はスチュワーデスとは言わず、キャビンアテンダント(客室乗務員)と呼ばれる。弁護士・志賀こずえさんの物語。

独立開業するならレンタルオフィス。「8士業はどこで開業する?自宅・マンション・レンタルオフィス比較」

資格学校と独学、どちらを選ぶ?「独学と資格学校、試験合格への近道はどっち?デメリットを徹底比較」
専業主婦から検事になって弁護士へ!

そのキャビンアテンダントの仕事をしてる時に結婚と退職をして専業主婦となる。
貧しい生活をしていた志賀こずえは大学に行く為の資金がなかった。
その為、大学進学を断念し、高卒でキャビンアテンダントとなる。
主婦になったものの、大学に行ってない劣等感が付きまとう。ある日、新聞で大学の通信教育制度を知る。
そして慶応大学の通信教育で法学部を卒業したが、劣等感は以前のままだった。
その劣等感を払拭すべく、最高難易度の司法試験に13回挑むのであった。

弁護士も仕事争奪戦?「弁護士でも就職難?女性問題に競争激化、資格剥奪のデメリットとは?」

名称独占と業務独占の違いはこちら「名称独占と業務独占の違い!その仕事に必要な国家資格とは?」
税理士の試験勉強を10年続けたシングルマザー。

23歳で結婚するも24歳で離婚。その後、税理士を目指した女性(丹羽和子)の物語。
「崖っぷちから始めたシングルマザーの税理士合格記」離婚後は子育てをしながら実家暮らし。
ある日、実家に来た姉が税理士になったら?と言われて税理士試験に挑戦する事を決意する。
税理士の受験資格がなくても諦めない。

税理士の受験資格、簿記1級を合格!
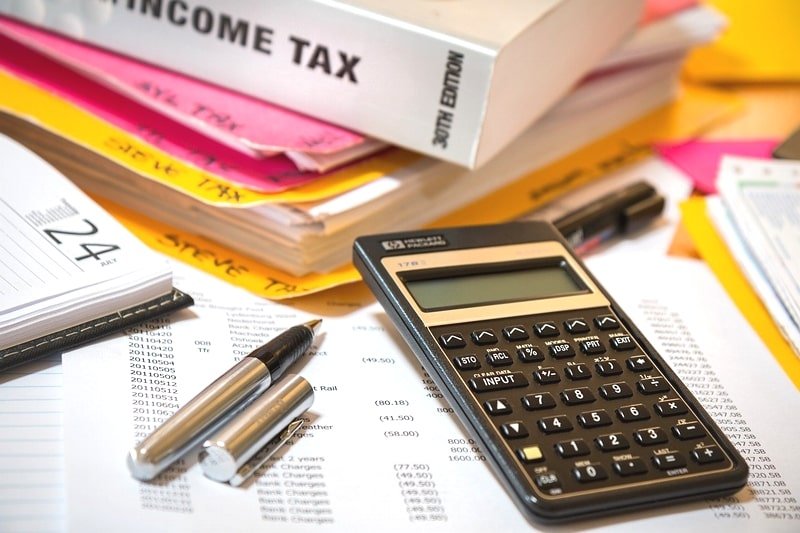
税理士の受験資格には様々なものがあり、短期大学の卒業や、大学3年生以上で受験するのが一般的。
高卒では受験資格がない(それは社会保険労務士も同じ)
それでも受験する為の方法を探し、簿記1級を取得して税理士試験に挑戦する。
子育てしながら税理士試験の勉強を続けて合格、独立を果たす。

簿記に独学で挑んだ話「簿記3級を独学合格する為のテキストと問題集を紹介!動画講義学習」

簿記の通信講座はこちら「簿記3級を独学合格する為のテキストと問題集を紹介!動画講義学習」
27歳の主婦が公認会計士試験に3度挑戦した物語。

次に紹介するのは
「子供を産んでから自分の夢を実現する!子育て主婦の公認会計士合格記」
で、公認会計士・税理士の小長谷敦子さんが書いた本。
何かを成し遂げたいと思いつつ、その何かを見つけられなかった。
公認会計士を目指すものの夫の理解が得られず、苦難の道程を進む。

国家資格で自立するならこちら「国家資格で自立できる?仕事とお金になる自己投資方法を紹介」

受験資格のない国家資格はこちら「受験資格のない国家資格6選!通信教育で誰でも合格、転職有利」
公認会計士の講座受講料は50万円?

ちなみに税理士と違って公認会計士は誰でも受験可能。
簿記2級取得後に1級を取るべきか、税理士や公認会計士を目指すべきか迷う。
だが、資格学校の受講相談で公認会計士の目指すと決意。
50万円の貯金を降ろして公認会計士講座を受講。公認会計士試験合格までの3年間が始まった。


社労士合格を目指すなら「社会保険労務士の試験対策!オンラインの通信教育講座で合格する」を読んでおこう。
社会保険労務士試験・開業実務関連記事。

- 社会保険労務士試験合格後、事務指定講習を受講して独立開業した。
- 実務未経験で社会保険労務士事務所に採用!勤務社労士の仕事内容。
- 人事や総務で書類作成経験は無くても社労士事務所勤務1ヶ月経過。
- 社会保険労務士事務所で勤務登録して2ヶ月経過その実務内容とは?
- 年度更新で概算確定保険料計算と雇用保険2年間の遡り加入手続き。
- 新人社会保険労務士の仕事は算定基礎届と労働者派遣事業報告書作成。
- 社会保険労務士試験前日の過ごし方!合格への直前対策と解答速報。
- 社会保険労務士試験に合格したら事務所に就職して実務経験を積もう!
- 社労士開業後の節税対策!青色申告65万円控除と会計ソフトでの経理。
- 確定申告の会計ソフト3選!経理を楽にして青色申告65万円控除。
















コメント